最近のテレビはつまらなくなったという声をよく聞きます。
これまで様々な番組を見てきたから、だいたいがどこかで見たことがあるはずだとか
昔と違って今は、色々な娯楽や刺激があるから、物足りないのだとかというような解釈もあるのでしょうが
もう少し根本的なテレビの問題について考えてみたいと思います。

なぜテレビがつまらなくなってきたのか、その原因は何なのでしょう
様々な要因について検討してみました。
テレビの番組制作費が少なくなった
91年にバブルが崩壊した後テレビの番組制作費が大きく減少しています。
日本はその後長い間、景気が回復せず、低成長が続いているのでテレビの広告費についても回復することはなかったのでしょう。
しかもそれだけではなく、テレビ以外の楽しみが増えたために、多くの人はテレビを観る時間が減っていて
それが視聴率の低下になり、スポンサーも広告費を増額しようとするモチベーションは上がらなかったと思います。
・インターネット
・ゲーム
・youtube
・ニコニコ動画
・Facebook
・ツイッター
・インスタグラム
など、1人の人に与えられている時間は有限ですから、他のことをすればテレビを観る時間は減ってきます。
また、バブル崩壊後、インターネットが急速に普及してきましたが
インターネットなどの広告の方が効率が良いので企業はテレビ広告を減らしてネット広告に予算をシフトしてきました。
インターネットに出す広告には
成果報酬型:商品が売れた場合にのみ報酬を支払えば良いもの
あるいはインターネットの閲覧履歴や、検索の内容から、閲覧者が興味を持つであろう商品や、購買意欲のある商品に絞って広告を表示する広告もあります。
企業はなぜテレビ広告からインターネット広告にシフトしているのでしょうか
そして、テレビ広告に使われる広告費が削られるようになった結果
いかに予算をかけずに、視聴率の取れる番組が作れるかに、テレビ局は腐心するようになりました。
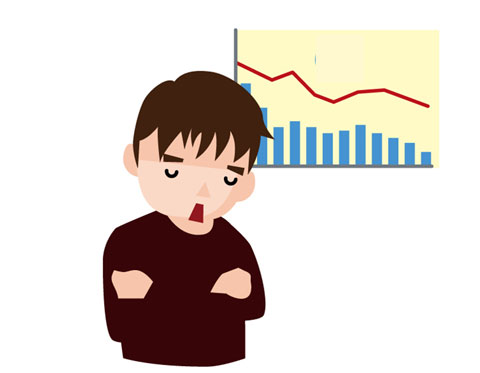
CMが増えた
最近は「生」でテレビを観る機会が減りました
「生」というのは、放送されているテレビ番組をリアルタイムで見ること
ほとんどの番組は録画して観るようにしています。
理由としては
・自分の都合の良い時間に観たい
・つまらない部分を飛ばしたり、情報番組などであれば倍速で見た方が効率が良い
という理由に加えて
・広告を飛ばして観るためもあります。
テレビは広告収入で成り立ってんだから、CMも見ろよと言う人もいるかもしれませんが
とにかくテレビのCMが長くて、頻繁に出てウザい
とてもじゃないけど番組に集中出来る状態でないほど、しつこくCMが出ます。
これじゃあいくら良い番組でも、せっかく感動したり、興奮している気持ちが完全に白けてしまいます。
テレビ局の収入が減ってるので、減収を補うためにCM枠を増やしているせいだと思いますが
私から言わせると、これがまたテレビ離れを起こす原因になってるんじゃないかと思いたくなります。

規制が増えて面白い番組が作りにくくなった
テレビには公共の電波という側面や、スポンサーなどの思惑もあり、様々な規制が増えて面白い(=過激であったり、とんがった内容)番組を作りにくくなったこともテレビをつまらなくしています。
規制や自主規制の原因となるのは
・BPO(放送倫理・番組向上機構)からの勧告やや視聴者からのクレーム
・スポンサーの嫌がる企画、企業イメージを損なう番組は作れない
ちょっと羽目を外した番組とかであれば、すぐに視聴者からのクレームが来てしまいます。
極一部の人のクレームであってもテレビ局としては無視するわけにはいきません
あるいは、クレームがくるような番組はスポンサーが嫌がったり
スポンサーが、企業イメージを傷つける番組を避けるようになれば、どうしても当たり障りの無い番組企画になります。

それに生番組とかであれば、出演者も無難な人を選ばざるを得なくなります。
・突拍子のない発言や行動をしない人
・視聴者やほかの出演者に嫌な思いをさせない人
・気配りのあるコメントが言える人
本当は突拍子も無い発言の方が面白いし、他の出演者が嫌がる内容でも、言った方が良い内容や、面白くなる場合も多いんですが
出演者も建前でしか話せなくなっています。
危ないことを話していると、出演依頼がなくなりますからね。
カジノの批判はしても、テレビに大量の広告を出しているパチンコの批判は出来ない
大食いやったら勿体ない、突っ込み入れたらいじめだなんて視聴者からクレームが来ます。
結局当たり障りの無い優等生が言うような「正解」ばかりで
チコちゃんじゃ無いですけど
「つまんねー奴だな」テなことになります。
中高年向けの内容に傾きがち
今時の若い人はネットやSNS、ゲームをやる時間が増えてきていて、あまりTVを見ないです。
しかも少子高齢化で、高齢者の割合がが増えていますし、
若い人より中高年の方が所得が高く、比較的に高価格帯の商品を多く購入する層ですから
スポンサーの要望としても、どうしても中高年の人が好みそうな番組内容になってしまいます。
そうなると益々若い人はテレビを観なくなってしまい、さらに中高年向けにスポットを当てた番組内容に傾くという流れに向かうわけです。

チャンネルや放送時間が限られている
今のテレビ放送の体制では、基本的に民放各局、地上波1チャンネル、衛星放送1チャンネルになっています。
放送時間も当たり前ですが24時間しかありません
その限られた資源の中で、テレビ局が収益を上げようとすればCMが高く売れる番組
つまり視聴率が取れる番組作りをする必要があります。
ぢゃあ、面白い番組を作れば高い視聴率が撮れるかというとそうでもありません
現代は個人の趣味や趣向は多様化してますし
他にも面白いことはたくさん有り
テレビの敵は他のテレビ局だけで無く、ゲームやマンガ、SNS、ユーチューブなど多岐に渡っています。
そうなると、どうしても万人受けする、誰もが観てもそこそこ面白い(一人一人の個人にとっては大して面白くない)
広い層に受け止められる番組が求められる結果、ありきたりな番組になりがちです。
一方
有料動画放送であれば、チャンネルも多いのでジャンルを絞った放送が出来ます。
普通のテレビ放送ほどスポンサーの意向を気にする必要も少ない
(お金をかけた映画などだと視聴人数の多い中国人にもウケる内容にするみたいな必要はありますが)
ユーチューブならTVの様な規制はほとんど無いし、数人しか見ないような内容の動画を出す事も出来ます。

現場の番組を作る能力が低下している
私はテレビ制作関係者じゃ無いので、外側から観た無責任な意見かもしれませんが
漏れ伝わってくるところや、日々のテレビ番組を観ていると、テレビ番組を作っている現場制作者の、番組を作る能力が低下していることも番組を面白くなくしている原因になっていると思います。
もちろんこれまで述べてきた、予算の削減や
低予算での部外の制作会社への丸投げ
各種の制約なども大きいとは思いますが
テレビを観ていると、どの局も同じような内容の番組ばかり
たまに面白い企画のものがあると、他の局も続々と同じような企画の番組が始まるようなことはよくあります。
あるいはちょっとした田舎のトピック的なお話を、ある局で流すと他局が同じ内容を次々と放送するなんてのもしょっちゅうです。
また、一部を除いて日本のテレビドラマは日本国内での視聴率獲得、つまりスポンサーからの資金獲得しか念頭になく、二次利用といっても再放送、あるいはDVD販売程度しか考えておらず、その場しのぎの番組作成になっているという話も聞きます。
一方、例えば韓国の場合、ドラマシリーズを海外市場に輸出することも視野に入れているので、主演の俳優には高額のギャラを提示することが出来、イ・ビョンホンクラスになると1話あたり1億円ともいわれていて
だから、俳優も、日本のようにいくつもの番組を掛け持ちでなんてこともできないし、その番組に全力を上げることになります。
さらに韓国などの場合、俳優もちゃんと俳優養成所でしっかりトレーニングをした人がなりますが
日本の場合は名前の売れたタレントがそのまま俳優として活躍するのが普通みたいにもなっています。

そのほかにも
最近、バラエティー番組が増えているのも
芸人に何時間も好き勝手にしゃべらせておいて面白かったところだけを抜き出してつなぎ合わせれば、そこそこ笑いも取れて視聴率も良い
作る方からすればお手軽なやり方で
ドラマなどをしっかり作り込もうというノウハウやモチベーションが無くなるわけです。
制作が簡単で、ワンパターンの番組の作り方をしていれば、手間暇も費用もかからないで一定の視聴率撮れることに安住し、結局似たような番組ばかりが出来てしまう結果になります。
それから現場の制作能力には直接関係ないかもしれませんが
大手芸能事務所が力関係で出演させるタレントや役柄をコントロールしている点も見逃せません
米国などでは制作するドラマによって、オーディションを行い最適な配役が決まるといった手順を踏みますが
日本ではキャスティングの主導権がテレビ局でなく、大手のプロダクションにあります。
芝居が出来るか、出来ないかよりも、このタレントでこういうストーリーで行きたいなどのプロダクションによる介入で決まっていくことが多くなっています。
そして、大手芸能事務所は、大物俳優とバーターで売り出し中の俳優をねじ込んだり
大手プロダクションの息の掛かった俳優ばかりキャスティングされるとか、この女優はキスはダメ、○○はダメなどという規制が入ったりすることもあるようです。
そのほかにも気に入らないタレントが出ている番組には自社のタレントを出演させないなどのこともよく聞いたりします。
また、前にも少し触れましたが、予算不足のため低価格で制作プロダクションに丸投げといった事が増えています。
乱暴な言い方をすれば
広告代理店がスポンサー企業からお金を集め、そこから広告代理店とテレビ局の取り分を取った残りが実際の製作費となる感じです。
お互い、お金を使わずそこそこの、視聴率が取れる番組が作れればそれでOK
飛び抜けた番組や、光る番組を作ってやろうなどというモチベーションは働きにくくなります。
加えて日本のテレビドラマとかはジャンルが限られてきます。
ほとんどのドラマは恋愛やサスペンス物です。
民放のドラマの場合、CMのスポンサー企業の商品に、化粧品など若い女性をターゲットにした物が多く
そうなると若い女性が好む恋愛物やあるいはせいぜいサスペンス物になってしまいます。
欧米で比較的人気のある政治物やSF物などを観る層は、広告を頻繁に出している会社の商品を購入する層ではありませんから、どうしてもそういう番組は作られなくなっていきます。

これからのテレビはどうなっていくのか
これからのテレビはどうなっていくのでしょう
などと、大上段に構えた章立てをしてしまってから
結局、考えてもよう分からんなと言ったところです。
とはいうもののある程度見えている部分もあります。
ユーチューブに流れる芸能人、TV関係者
テレビはつまらなくなりつつ、少しずつ斜陽化しています。
取り敢えず、ライバルとして上がってくるのがユーチューブ
ある大物芸能人さんが、
「ユーチューブは敵やんか」
と冗談めかして話してましたが
実際これは真実で、最近はネット広告、特に動画広告がものすごい勢いで伸びていて
(企業が使う広告費が2019年にネット広告がテレビ広告を逆転しています)
テレビ広告費が減少すれば、間接的に芸人さんやタレントさんの収入は減少します。
ユーチューブというと以前は素人さんの一発芸がウケれば視聴回数が増えるみたいな感じでしたが
ここ1、2年で動画の質は格段に上がってきています。
ユーチューブ自体が、低レベルの動画を排除する方向にあるのに加え
有名ユーチューバーなどは、専門の動画編集者に、編集を外部委託したり
テレビで活躍できない芸能人が、ユーチューブに活路を見いだしたり
あるいは、ユーチューブに将来性を見いだしてあえてテレビではなく、ユーチューブを活用する芸能人やアーティストも増え
それに引かれるようにこれまでテレビの動画などを専門にしていた動画関係者が、次第にユーチューブの分野に乗り出してくるようになっています。
もっとも、ユーチューブもウザいほどCMが出るようになってきて、今後どうなるかなって気もします。
CMを消すためにわざわざお金を払ってまでユーチューブを見る人は、今のところそんなにいるとも思えないし
といってもユーチューブの動画の質が上がってくればお金を払ってでも見る人が増えるのかもしれません
有料動画放送を見る人が増える
テレビ番組の質が下がるのに反比例するかのように、有料動画放送(ペイテレビ)を視聴する人が増えています。
Netflix、DAZN、Amazonプライムビデオ、U-NEXT、Hulu、dTV、スカパーなどなど
様々な有料動画サービスがしのぎを削っているのが現在です。
米国では、多くの人が有料のケーブルテレビを視聴し、無料の地上波TVを見るのは低所得層みたいになっていますが
日本でもそういう方向に向かって行くのでしょう
有料動画ならしつこいCMもなく、質の高い、しかも万人受けする内容ではなく、コアな視聴対象者を想定した、比較的マニアックな内容の番組も見ることができます。
日本でも、今後はお金を払って、有料動画サービスを利用する人が増えていくのでしょう。
そうなれば、ますますいわゆるテレビ(地上波放送)を見る人は減少し
企業が支払う広告費も減少し、番組の質は更に低下するという負のスパイラルが始まるかもしれません
現状のBS放送を見ていると、TVショッピングや、昔のドラマの再放送、韓ドラや昔の洋画を垂れ流すような感じになっていますが
地上波放送も、BS放送のような感じになっていく可能性もあります。

今後地上波テレビは加速度的に衰退するのかも
企業がインターネットに支出する広告費がどんどん増えていることで2019年にネット広告費がテレビを逆転しましたが
企業がテレビに出す広告は、実はそれほど減少していません
テレビがつまらなくなった、見なくなった人が増えたといっても、まだまだテレビの影響力は大きいです。
しかし、これからも地上波テレビの地位の地盤沈下は止まらないでしょうし
ある一定のレベル以下に下がれば、一気に加速度的にテレビが衰退していくことも考えられます
まとめ
様々な要因が重なり地上波テレビはつまらなくなり、視聴しない人も増えています。
これまでテレビが持っていた絶対的な影響力は今後低下していきネットやSNSの影響力が高まっていくのでしょう。
これは歴史的な必然なのか、あるいはテレビが新たな価値を生み出すようになって、ひき続き影響力を保ち続けるのか現時点では明確なことは分かりませんが
少なくとも昭和の時代のような圧倒的なメディアとしての力は低下していく可能性は高いです。
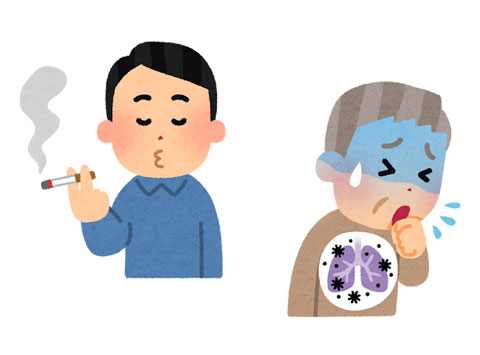

コメント